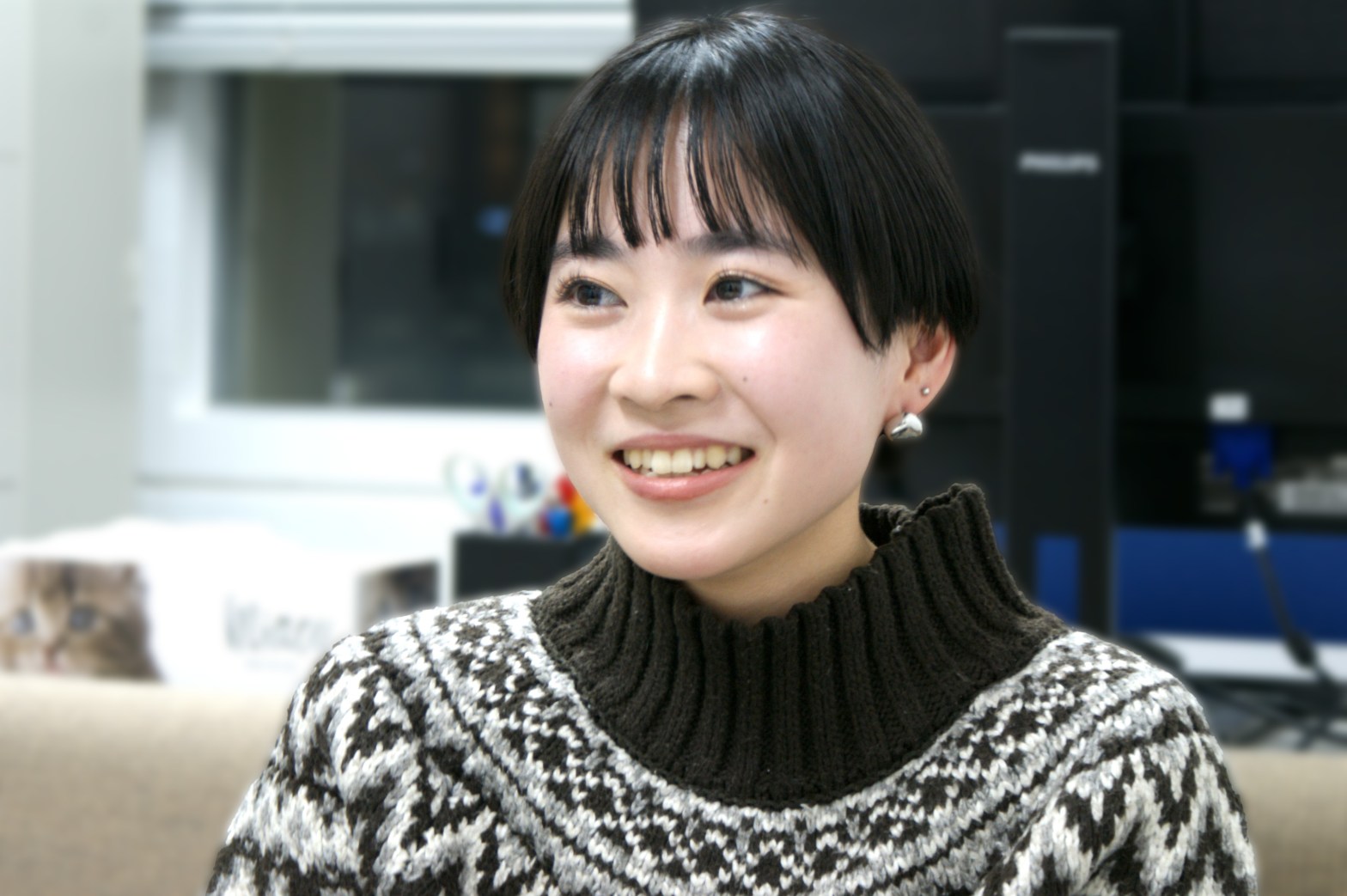杉田真衣 さん
博士前期課程英米文学専攻
カズオ・イシグロの難解さをひもとく
Q)今日はお忙しいところありがとうございます。まずは杉田さんのご研究を、一般の方々や、とくにこれから大学院に進学して勉強してみたいと思っている人たちに対して、魅力的にアピールしていただけますか。
A)わかりました。わたしは、カズオ・イシグロという作家の作品について研究しています。卒業論文では、『わたしを離さないで』(以下『わたし』と略記)という作品をとりあげましたが、修士論文では、『遠い山なみの光』(以下『山なみ』と略記)に取り組みたいと思っています。
Q)両方とも映像化されている作品ですね。
A)そうですね。ちょうど今年、『山なみ』の映画が公開されていますね。わたしがイシグロに出会ったきっかけは、英文学科の松本(朗)先生の授業だったんです。イシグロはとにかく、人間の記憶のあり方とか。人間がどういうふうに、意識的または無意識的に記憶を隠蔽したり改竄したりするのか、そういうことにかなり深く切り込む作家で。わたしは大学に入るまで、そういうことを意識したことが一切なかったので、人間の記憶ってここまで複雑なものなのか、自分でも意識せずに忘れようとしていたり、改竄してしまったりすることがあるんだと知って。いままで知らなかった自分の内面を言語化して知っていくみたいな、そういう楽しさを覚えたんです。
Q)そういう体験を、一般の方々にもぜひしていただきたい、ということなんでしょうか。
A)そうですね。一般の方が読むと、ちょっと難しくて何を言っているのか分からないという作家でもあるので。わたしは、イシグロがどういう作家でどういう手法を使ってどういうことをしたいのか、それをある程度知っている状態で読んだので、「なるほどこういうことか」と読んでいるうちに分かってきたり、「ここに何かイシグロの言いたいポイントが詰まっているんじゃないか」と自分で察知できるようになってきているんですけど。個人的には、とくに『わたし』は、一般の方でも引き込まれるところがかなり多い作品かなと思っています。『遠い山なみの光』はかなり難解で、表層の部分だけを掬っていくような描き方をするので複雑なんですけど。『わたし』のほうは、主人公がすごく歪んだディストピア社会にいるのに、その社会の本質に気づいておらず、自分は人間性を持っている普通の存在だと信じ込んでいる状態ではありますが、恋愛とか友情とかいままでの人生で起きたことを情緒溢れる語り口で語る部分は、リアリティに溢れていて一般の人にも刺さるんじゃないかなって思っています。
Q)実はぼくも歴史学者で、歴史の改竄や集合的忘却の研究をずっとしているので、カズオ・イシグロの問題意識は非常によく理解できるところなんです。やっぱりいま、例えばプーチンの歴史政治にしても、集合的な歴史を故意に歪曲・喧伝することによって、一般に信じさせるようなことが行われていますし、ポスト・トゥルースの社会のなかで、SNSなどでも毎日その種の言説が繰り返されているわけですよね。そういう意味ではカズオ・イシグロの作品は、いまこそ現代への警鐘として読まれる価値があるますよね。しかし一方で、やっぱりいまお話しされたように、一般の方が読むには難しいところがあるとすれば、その意義や重要性をどう社会へ分かりやすく届けるかも、もしかしたら研究者の大切な仕事かもしれないですよね。杉田さんはアカデミアに足を踏み入れたばかりだと思うのですが、最終的にどうでしょうか、将来目指されているところはありますか?
A)難しくて手を出せないという方を減らしたいな、とは思います。例えばNHK教育の『100分 de 名著』などをみると、すごく難しそうな本でも手に取ってみようかなと思える教え方をされているので、そうした取り組みができる研究者になりたいですね。
ひとの思考のオリジンを辿る
Q)なるほど。学部のときには、「イギリス文学と教育」のような学部生シンポジウムに登壇されたと伺っていますが、やはり教育にも関心をお持ちなんですね。
A)そうですね。わたしは、「どうしてひとはそういうふうに考えるようになったんだろう」とか、「どうしてそういう思想を持つようになったんだろう」ということについて考えるのがすごく好きで、家庭環境だったり学校の教育だったり、何かしらオリジンみたいなものが絶対にあると思うので、そこを理論化して説明できるようになりたいなとずっと思っているんです。卒論も、最終的な結論は別のところにあったんですけれども、第1章では教育に目を向けていて、そこからスタートしたところがありまして。わたしはそもそも卒論で、『わたし』とジョージ・オーエル『1984』を比較して書きたいなと思っていたんです。そのきっかけは、『わたし』読んでいるとき、「どうして主人公は、死に対する恐怖を一切感じていなくて、すごく呑気でいられるんだろう」という理解できなさを感じ、その原因を辿っていったことです。そこから、ヘールシャムというキャシーが育った寄宿学校の教育に、何か歪みがあるんじゃないかと思えてくるんですが、キャシーは自分が置かれているディストピア社会の本質を見抜けないように洗脳されている語り手なんですね。でもわたしは、『わたし』を読む前にオーエルの『1984』を読んでいまして。「『1984』の主人公のウィンストン・スミスは、キャシーとは違い、どうしてディストピア社会に抵抗しようって思えたんだろう」って、そのあたりの差が見えてきたわけですよ。それで、もう1回『1984』を読み返してみたら、ウィンストンは過去に、母親や幼い妹と無理やり引き離された記憶があるんですね、それを夢のなかで反芻する描写があって。そういうふうにディストピアに至る前の、人間が自然に情緒的関係を築いていた、過去の時代の何かしら片鱗みたいなものが自分のなかにあると、それと比較して現状のディストピア性が見えてくるじゃないですか、やっぱりこれおかしいって思えるので。でも、キャシーの場合はそうじゃない。じゃあなんでだろうって考えていくと、彼女は生まれた時からディストピアしか知らないから、こうなってしまったんじゃないかと。そういうふうに人の思想とか価値観、考え方の源泉みたいなところを辿っていく楽しさを、常に持っているんです。
Q)比較対象として、自分のなかにあるオリジンの欠片というか、そういうものがあるかないかで生き方が変わってくる。しかし、何もないひとは従順なだけなのかというと、多分そうではないだろうと思うんですよね。そういう抵抗がどう生まれてくるのか、すごくいま大事なところだと思いますね。
ディストピアのなかの希望
Q)アトウッドの『侍女の物語』にしても、貴志祐介の『新世界より』にしても、『わたし』とよく似た、歴史と記憶に関わるディストピアの物語が、ある時期から内外で多く発表されているように思います。ポスト・トゥルースの時代を反映しているのでしょうが、しかし絶望ばかりではなくて、そのなかに何らかの希望を見出せるようにしている気がしますね。
A)そうですね。加藤めぐみさんが、『侍女の物語』をポスト・ヒューマンの文脈で説明されているのですが、『わたし』をポスト〜といいきれるのかは少し疑問なんですね。やっぱりディストピア小説が成り立つのは、何か人間のなかにディストピアと相容れない人間性の本源みたいなもの、捨てられないものがあるからなんだろうと思うんです。『わたし』に関していいますと、人間的な部分と非人間的な部分を行き来している、あわいに立つような存在=クローンについて描いているのですが、けっこうその人間的な語りが前面に押し出されているように感じるんですよ。だから一般の方も、一応最後までは読み切れる人が多いはず、なんかちょっと面白いし共感できるところもあるしっていう。でもやっぱり根底のところにはディストピアから逃げ出そうとしない、なんかちょっと人間的とはいいきれないような、受動性とでもいうべきものもある。一方で先生が仰ったように、ディストピアに完全には屈服しない、無意識的にでも抵抗してしまう本能のようなものも、部分的に描かれている。作家や作品によって違うと思うのですが、その対比性がディストピアの特質を浮き彫りにしていくので、大事だなと思います。
Q)『1984』なんかもそうだと思うんですが、ディストピアに対して最終的に革命のようなものが起こるという、ある意味ではマルクス主義的な物語の作り方と、結局ディストピアを受け容れていかざるをえない、そのなかでしか生きていけないという人びとの弱さをどう考えるのかという深さ、慈しみがあるように思うんですね。例えば戦争や震災の後に、「忘れるな」の大合唱が響いてきますけど、本当に辛い体験をしたひとは忘れなきゃ生きていけない、正対したら生きていけないところがある。とすれば「忘却」は優しく大切なものだし、かといって社会全体が忘れてしまえば同じようなことが繰り返されるかもしれない。いちばん弱い人びとが生存していくためには最低限何が必要なのか、何を許して何を許しちゃいけないのかということを、最終的に問おうとしているのかなという感じがするんですよね。
A)まさにそうですね。弱い立場のひとに寄り添うと口でいったら簡単ですけど、その方法をちゃんと理解しているひとってなかなかいないんだろうなと思って。わたしも大学に入ってそういうことを学んで、 例えば忘れるだとか、ある程度嘘をついてでも嘘混じりでも人に話すとか、それで自分の記憶をある程度改竄していくとか、そういうことが必ずしも悪いことじゃなくて、むしろそういうトラウマ的な出来事と自分との折り合いをつけていくみたいな、そういうことをイシグロはかなり中心的に描いていると思うので。『山なみ』もそういう小説で、主人公=語り手の悦子が自分の都合のいい記憶だけ引き出して、都合の悪い部分はちょっとねじ曲げたりとか、そういう語りをするんですけど。映画のほうもちょっと観たんですが、最後のほうとかかなりホラーっぽい演出が多くて、ちょっと怖いな、暗いなって思わせるような描写が多いんです。でもわたしは、その暗い過程を踏み台に、未来への一歩を踏み出すっていう描き方を、イシグロはしているんだろうなと思って。総合的に見たらすごく暗い小説であるように見えるんですけど、でもイシグロは、むしろ希望の一歩として描いてるんだろうなと思います。
 文学研究科委員長室にて。少し緊張気味に話が始まる。
文学研究科委員長室にて。少し緊張気味に話が始まる。
主観は意外と理論的に説明できる
Q)そもそも杉田さんが、大学院に進んで研究を続けていこうと思われたのは、ちょっと自己物語化になっちゃうかもしれないのですが、どういうところに画期があったのでしょう?
A)もともと中学・高校のときとかは、飛び抜けて勉強ができたというわけでもなく、むしろ劣等感しかなくて。周りはなんでこんなにできるんだろうとか、自分の嫌な部分ばっかり見えていました。別に高校教育を否定しているわけではないんですが、やっぱりどうしても受験のための勉強になってしまうじゃないですか。短期記憶ですぱすぱ効率よく覚えて、それをいかに使って点数を取っていくか。自分はそういう勉強法にずっと違和感を覚えていて、もっと長期記憶的に勉強したいなとか、世界史の用語集を読むよりも世界史の史料集を読んでいるほうが好きとか、もうちょっと深く物事を考えるほうが好きだし向いてるなとずっと感じていて、その欲求が満たされたのが大学だったんです。大学に入って、1時間が100分の長い授業でじっくりと作品を扱ったりとか、そういうところが私にはまったというのもひとつですが、他にも先生方が素晴らしすぎて。本当に先生方の授業で人生変わったなって、いつも思うんです。
Q)こちらのインタビューに出てくださる方は大体そう絶賛されるので、僕はつまんないなと思っているんですけど(笑)、本当なんですね。
A)気を遣っているわけではないんです(笑)。 すごくよく覚えているのが、大学に入って1回目の授業。初めて文学の講義を受けたときに、いままで文学を勉強したことがなかったので、読書感想文みたいなリアクション・ペーパーを提出したんです。ここが面白かったとか、そういうことしか書けなかったんですけど、評価が返ってきて、確かCとかだったんですよ。何でだろうと思って。本の解釈の仕方なんてひとそれぞれ違うので、どうやって評価しているんだろうと疑問に思っていたら、先生がその次の授業でフィードバックをしてくださって。文学の分析の仕方について、初歩の初歩を見せてくださったんですが、それが意外と科学的だったところが、何だか刺さってしまったんです。「面白かった」の一言だと、自分の主観に過ぎないじゃないですか。主観を超えて、そこからどう理論的に説明して他人に伝えられるか。まずはその自分の主観がどこから生まれたのかについて、テキストの細かいエビデンス、データを蓄積していって、問題の語句や表現が一箇所だけではなく、他にもいろいろなところに散りばめられているのを確認するとか、作家自身の思想を調べてみるとか。他にも、一人称語りだったら、訛りから人物の階級が読み取れたり、話題の選び方から思想が見えてきたり。エビデンスって、調べたら調べるだけ出てくるので、そういう作業をして、自分の主観を理論的に組み換えていく、他人に説得的に説明できるようにするっていう、そういう文学分析の仕方を教えてくださったんですね。もう目が覚めたというか、主観って意外と理論化できるんだって。自分のなかでいままで閉じ込めていた感情が、意外とひとと共有できるんだっていう可能性を知って、目が覚めた感じがしました。
Q)いいお話ですね! フィードバックって、やっぱりちゃんとしなきゃいけないんだ…。杉田さんが、中学とか高校のときにもやもやしていたものって、自分が思っていることや考えていること、それが正確にひとに伝わらなかったり、あるいは自分自身でそれをどう表現するのか、言葉とか方法とかがあまり分からない。そういうところで自分自身を表現できないし、相手にも伝わらないしで、いろいろもどかしい思いをずっとしていたっていうことなんですかね。
A)ずっと孤独感があって、ディスコミュニケーションなんですけども、本当に完全に自分が独りになっていて。自分のなかで消化しきれない感情があるのに、それを表現したら、人を傷つけてしまう言い方になるんじゃないかとか。気を遣ったりとか、単純にこんなことを考えている自分は恥ずかしいと思ったりとか、そういうことばっかりだったんですけど。でも、どうして自分がそういう感情を秘めたいと思っているのか、隠したいと思っているのかっていうことすら、言語化できるっていうことに気づいて。いま言語化の孕む暴力性や危険性も学んでいるところなので、一概にはいえないですけど、そういうふうに自分を表現する術みたいなものを、文学の研究を通じて教えてもらった気がします。
Q)杉田さん自身の、言語論的転回ですね。中学・高校は孤独だと仰ったんですけど、友だちでも教員でも、やっぱり同じ問題意識を共有できる仲間は、あまりいなかったんでしょうか?
A)そうですね。そもそもわたしが、そういうもやもやを抱えていることを恥としていたので、隠していたわけですね。こういう教育ってどうなんだろうとか、先生にはもちろん同じように受験を頑張っている子たちにもいえないし、そもそも自分の勉強の仕方にも自信がなかったので。言語化したいとすら思わなかったんです。
Q)でも、それではなぜ英米文学を専攻に選んで、上智大学に来られたんですか?
A)単純に本を読むのが好きだったからで、すごく深い理由があるわけではなかったんです。英語はもとからちょっと得意で、高校時代はそこにアイデンティティを見出しているところがあって。英語だけが得意で、ほかは本当に一切苦手だったので、自分には英語しかないと思っているところもあって。でも、その英語もどんどんほかのクラスメイトに抜かされていって、すごくしんどかったんですけど…。でも物語については、「赤毛のアン」シリーズとか、「ハリー・ポッター」シリーズとかも大好きで。ハリー・ポッターとかはもう読みすぎていて。
Q)自分の本心を隠しながら、建前的なところで選べる進路が、とりあえず英米文学だった。そうすると、そこでいまの展開に出会えたってというのは、すごく幸福なことですよね。
A)幸運だったと思いますね、偶然に過ぎないのですが。英米文学の方向に進もうっていうのは、受験の当時から決めていました。どの大学を受けるにせよ、英米文学科に絞っていたんです。上智大学に絞ったのも正直なところ、自分が合格できそうなレベルで一番高いところを目指そうっていうだけだったんです。だから、本当に入ってみてびっくりしました。大学に入ったらサークルとか入ってみようかな、大学生っぽくいろんなカフェに行ったりとか、そういうキラキラした生活を送ってみたいなとか思ってたはずなのに、入ってみたら勉強が楽しくて。わたしはサークルよりも勉強だと思って、本当に没頭してしまって。授業が終わった後も、プリントを読み返して先生が仰った言葉を書き留めて、こういう言葉の使い方があるんだとか、先生の話し方から学ぶところがあったりとか。どんどん道が開けていったのも、まさに幸運だったなって思います。
Q)指導教員の先生が羨ましいですね、こういう学生さんがいらっしゃって(笑)。そこで一気に花開いて、まさに世界が変わったっていう感じですね。
A)まさに世界の見方が変わりましたね。
「救いのなさに救われる」
Q)先ほど、カズオ・イシグロの文学にも大学の授業で出会ったと仰っていましたが、それまではまったく?
A)まったく知らなかったです。
Q)映画もドラマも観ていなかった?
A)はい、まったく知らなくて。
Q)では、数ある作家・作品のなかで、なぜカズオ・イシグロを選び取っていくことになったんでしょう?
A)それはもうディストピアだから、という理由に尽きます。カズオ・イシグロはディストピア作家というだけではなくて、いろんな小説を書いているわけなんですけど、とにかく授業で扱った「わたし」のディストピア社会がすごく刺さってしまって。
Q)それは、もう昔からの興味・関心で? あるいは大学に入ってからでしょうか?
A)大学に入ってからですね。中学・高校とかは、まさに「赤毛のアン」とか「ハリー・ポッター」とかそういう話が好きで。まあ完全なディストピアとはだいぶ違うと思うんですけど、ディストピアの「救いのなさに救われた」みたいなところがあって。生きているなかですごく辛いことがあったときに、その状況から完全に救われることってないじゃないですか、ほとんど。で、そういうところにすごくフラストレーションが溜まって、泣いていて。皆さんそうだと思うんですけど、いろいろ人間関係とか勉強について、自分よりももっとつらい人もいるはずなのに、自分がこんなに悩んでるのはそれこそ恥ずかしいとか、自分独りだけがこんなにきつい目に遇ってるんじゃないか、みたいに自己憐憫に浸ったりして、閉じこもっちゃっていたんですけど。そういうときに、「いや努力は報われるよ」とか「いまはつらいけどいつかどうにかなる」とか、そういう聞こえのいい言葉をいわれるのが耐えられなくて。より孤独感を抱いて、このひとはもうすべてそういう悩みから解放されてるからいえるんだって、生存者バイアス的な発言に思えてしまって。だから、そういう偽善の言葉で丸め込まないで、淡々と現実を突きつけてくれるディストピア小説に救われてしまって。「わたしが見たかった世界はこういうのだ」とか、「わたしがいってほしかった言葉はこういうのだ」っていうものが、ディストピア小説に詰まっていたのが、救われるというか、自分って独りじゃないんだなって思えたんです。誰にも教えてもらえなかったことを教えてもらったような、満足感や納得感がありました。
Q)なるほど。東日本大震災のあとに、ぼくも一時期文学が読めなくなったことがありまして。ずっと好きでいろんなジャンルのものを読んでいたんですけど、文学に書かれていることにまったく魅力を感じなくなっちゃったんですね。大事なことが書かれていると思えなくなってしまった。逆に、事実だけを淡々と追うノンフィクションを読んでいると安心したんです。もしかしたら、そういう経験とどこかで繋がっているのかもしれないですね。そういう意味でいうと、杉田さんが中高生のときからずっと抑圧していたものは、震災に匹敵するくらいの経験というか、ご自身のなかでは、それくらいの重みがあったことなのかもしれない。やっぱりそういうなかで、ディストピア、そしてカズオ・イシグロが一番心地よかったっていうことなんですかね。
A)そうですね、読んでもまさに心地よかったというか。あのときの自分が抱えていたフラストレーションは間違ってなかったんだな、孤独でもないし、別に恥ずかしいわけでもないし、それがある意味人間の本質みたいなものなんだなっていう、安心感みたいなのがありましたね。
Q)そうですよね。公明正大なものを見せられても、やっぱりその嘘臭さが際立ってきちゃうっていうことはありますよね。
A)結構ひねくれてたんだなって思いますね。ひねくれがこういう風に爆発してしまって(笑)。
Q)ディストピアにもいろんな描き方ってあるじゃないですか。マニアックな話になりますけど、1970〜80年代に未来の描き方が、手塚治虫的なバラ色の明るいユートピアから、例えば環境破壊が進んで酸性雨が降り続いているような、『ブレードランナー』的な陰鬱なイメージに変化してきた。もはや、そういうディストピアにしかリアルさを感じないようになってしまった。そうしたなかで、杉田さんが一番しっくり来る、心地よいディストピアっていうのはどんなものなんですかね。
A)まず、イシグロの記憶の歪め方っていうのはひとつ。やっぱり、心理とか記憶が関わってくるところですかね、リアリズム追求だけではなくて。 結構わたしは文学を心理的に、精神分析とかを使いながら分析するのがすごく好きなので。
Q)先ほども主観の話をされていたので、ディストピアを客観的に描き出すより、それを人びとがどう捉え、そのなかでどういう思いや感情を抱きながら生きているのか、そういうところに拘っていくわけですかね。
A)一言でいえば〈語り〉ですかね。ディストピアをどう語るかっていうところが。
Q)お、全部繋がってきますね。言語論的転回とか、ナラティヴの問題に。
A)ナラティヴの問題はもうとにかく深くて、人間のいま考えていることとか、過去に考えてきたこと、逆に、考えないように抑圧してきたこと、無意識的に刷り込まれる価値観、複雑な精神状態とかの表層部分が〈語り〉だと思っているので。だから、改竄された記憶とかも語りに表れますしね。『1984』と『わたし』の共通項としては、言語の改竄の問題が挙げられるんですが、『1984』にはニュースピークがありますし、『わたし』にもヘールシャムで言語を改竄して教育する手法が採られています。例えば、洗脳者側が「死ぬ」っていう言葉を使わずに「命を終える」とか「完了」と言い換えて、残酷さや痛ましさを排除するような書き方をしていたりとか。そういう言語の改竄や歪み、言葉が特定の語彙を失うことが人の思考にどう影響するのかとか、そういうところも〈語り〉に表れてくるので、一言でまとめれば〈語り〉です。その背後にある、語り手の脳のなかにある言語形態とか、あるいは心理とか、トラウマ的な記憶だったりとか。そういうものがぐちゃぐちゃに絡み合って現れるのが、〈語り〉だなと思います。
Q)面白いですね。杉田さんの興味関心が、全体としてすごく一貫性を持って成り立っていることがよく分かりました。
Q)では、語りに対する興味関心は、どのあたりから出てくるんでしょう?
A)やっぱり大学の授業ですね。それまでは、そもそも語りという言葉すら知らなかったんです。語りのタイプでも、わたしはイシグロ的な一人称語りが好きなんですけど、中学や高校で読んでいた本は、『赤毛のアン』も『ハリー・ポッター』も、ヘルマン・ヘッセの『車輪の下』、三浦綾子さんの『氷点』とか、全部一人称視点じゃないんです。むしろ、一人称視点の本って読んだことあったかなっていうくらいだったので、新鮮味があったのかもしれません、こういう書き方もあるんだなと思って。一人称の語りって、すごく現実に対して忠実な書き方じゃないかなって思うんですね。 嘘が混じるぶんありのままというか、そういう書き方じゃないかなと。たぶんそこに大きな発見があったんだと思います。
Q)客観的な、第三者的な形で物事を描いていく書き方と、主観で描いていく書き方では、読者の経験がどう異なるのか。文学にはいろいろな分析方法があると思うんですけど、やっぱり杉田さんは、書き手のありようそのものを、自身も体験されていくことに関心があるのでしょうかね。
A)体験するというより、ひねくれているので、そこに突っ込みを入れたい感じはありますね。その世界に没入して新しい世界を見るというよりかは、どうしてこういう書き方になるのか、最初から結構批判的に読んじゃっているところがあるので。自分は常に世界を批判的に捉えているので、その見方と語り手の見方がどう違うのか、ギャップを見ていくっていう。
Q)例えば全身を包む服があって、誰か別の人の服だと認識はしているけど、それを着てみたときにどこにどう違和感があるのか。身体感覚も含めて確かめていきながら、その理由を追求していく感じですかね。ちょっとブカブカだなとか、ちょっときついなとか、そういうのを自分で感じながら、じゃあなんでそうなってしまうの?って。
A)カズオ・イシグロ作品以外にも、いろいろ援用できると思うんですよ。外在的にアプローチもしながらっていうのが楽しいなって、すごく思います。
 話が転がり始めると、どんどん言葉が紡がれていく。
話が転がり始めると、どんどん言葉が紡がれていく。
ディストピア文学の未来
Q)ご自身のことでも研究のことでも、未来とか将来を見据えていくっていうことは、まだあまりないんですか?
A)そうですね、とりあえずいまは、カズオ・イシグロに集中したいなと思っています。結構自分の好みを研究にしていると思うので、語り、ディストピア。 ディストピアのナラティヴについて。そういう方向性ではいきたいなと。でもやっぱり文学研究の面白さって、自分の好きなところだけを追求するのでは、満たしきれないところがあると思うので、他の文学とかも読んでよそ見しつつというか、違いを考えながら取り組んでいきたいです。
Q)先ほどもいいましたが、ディストピア小説って、時代や世界のありようと密接に関わっていると思うんですね。しかし、これほど世界そのものがディストピア化しているとき、これからディストピア小説ってどうなっちゃうんだろう?と。それでも必要とされるのか、あるいは、現実の苛酷さが度合いを増して、逆に文学の世界ではディストピアを描けなくなっていくんじゃないか。そのあたりはいかがですか?
A)そうですね。確かにディストピアとリアルの境目がどんどん曖昧になっていくところはあると思うんですけど、文学とリアルが完全に一致することはおそらくないと思いますし、ディストピアにもいろんな種類があるので、政治的な部分に焦点を当てるかとか、アトウッドみたいに女性に焦点を当てるかとか、いろんなディストピアの描き方があることを考えたら、そんなに完全に一致することはないんだろうとは思いますね。でも確かにアトウッドとかは「予言する作家」みたいになっていると思うので、 そういうふうに小説のほうにリアルが追いついてきているというか、現実が芸術を模倣するみたいな感じになっちゃいますけど、そういうことが実際に起こりうるんだなっていう怖さはかなり感じます。でも、ディストピア小説の描き方はまたどんどん変わっていくのでしょうし、小説にあるディストピア社会がいま現前したとして、そのなかで生きている人びとがさらにどんなディストピアを想像するのか、もう予測することができないですね。
Q)杉田さんが見ようとされているのが、人を通したナラティヴとしてのディストピアなんだとすれば、どのような時代・社会でも、ひとの数だけディストピアがありうるということですよね。極端なことをいうと、手塚治虫的な明るい未来こそがもうディストピアなんじゃないか、という捉え方もできるわけですもんね。
A)わたしの実体験としては、ディストピアを見たからこそ、自分のどういう要素が、自分を人間たらしめているのか実感できるところがある。いままでしんどいなとか、運ないなとか思いながら生きていても、ディストピアを見ると、簡単に言えば、自分ってすごく恵まれているなと。自分でも意識していないような、ある意味、恵まれてるがゆえに、意識せずに済んでいた根本的な問題が、自分を人間として存在させていることに気づくことがあります。
文学は誰にとっても「役に立つ」
Q)大きな話ですが、人間存在にとって、なぜ文学が必要なのかという点はいかがでしょう。
A)逃避先みたいな、避難所みたいなふうに、わたしは考えています。
Q)アジールですね。
A)中学とか高校のときに、『赤毛のアン』や『ハリー・ポッター』にはまっていたのは、そのときたぶん辛かったからなんだろうなって思います。現実が辛い、現実を見たくないと、どうしてもそういうハッピーエンド的なものにすがりたくなる。大学に入って逆にディストピアに向かっているのは、たぶんいまは自分の生活に満足してるからなんでしょう。二つの読書傾向の共通点を見ていくと、どっちもある意味逃避先になっているなって思います。中学・高校は辛い現実から逃げるために本を読んで、笑って現実のことを忘れてっていうことをして、大学ではいままでモヤモヤしていたことを発散させる先で、自分は独りじゃないし過去も独りじゃなかったって、これまでの自分を肯定するためのよりどころみたいなものとして、避難所みたいな感じで捉えてますね。どんな状況に置かれても、文学の世界を探れば理解者が見つかる、という希望もありますね。
Q)人間があらためて人間になるために必要な媒体というか、そういう感じなんでしょうかね。
A)まさにイシグロは、そういう辛い現実にどう折り合いをつけていくか書いている作家でもありますし、イシグロ自身も文学として表象することを通じ、自分の職業としてそれを体現しているみたいな。どの作家も誰かにとっての避難所、そういう存在なのかなというふうに思いますね。
Q)避難所っていうのはそうなんだろうなと思うんですけど、杉田さんにとっては文学自体、同胞みたいなものなのかもしれませんね。
A)そうですね。
Q)先ほど、かつては同じ問題意識を共有できる仲間がいなかったと仰っていましたが、そういう杉田さんにとって、文学こそが同胞として常にあって、だからこそ一人称で語ることが大事なのかもしれない。
A)確かに、自分が感じていることをうまく言語化してくれているキャラクターに出会うと、親友に出会ったような気がしたりするんですけど。でも面白いなと思うのが、現実の状況と逆行するような話を好む性質が自分のなかにあって、だから中学とか高校とかすごく鬱屈とした時代には、ハリーポッターみたいなヒーロー的な像に憧れたりとか、ある種同一化しようとしているところもあると思うんですけど、赤毛のアンみたいに常に明るくて人を笑わせてみたいな、何か失敗してもうまく乗り越えてっていうキャラクターのことを読んで、あ、いいなって憧れるところもあって。逆に、いまディストピアの世界に生きているキャラクターたちを見られるのは、自分が過去のことをある程度割り切れているからなんだろうなって思って。でも同じような体験をしている人を見ると、過去の自分が救われるみたいな、過去の自分を含めたいまの自分も救われるみたいな、 そういう体験があるなと思うので、同胞でもあり、まったく逆の精神状態にいる相手でもありって、ちょっと二重的な感じがします。
Q)場合によってはハリーポッターも、今後、中学・高校のときに見ていたものとは違う視点で向きあうことになるかもしれないですね。例えばハリーの特別性って結局は血なのかって考えると、やっぱり「世襲」の話でそれなりにディストピアですよね。
A)わたし、大学に入ってから一番好きだなって思うキャラクターが変わって、それがロンになったんですよ。ハリーの影に隠れて、いつも自分が注目してもらえない。それをついに最終巻で爆発させてしまうっていう。もうその感情のはけ口がいつまでも見つからないみたいな。ああいうロンがすごく好きで、だからそういう読み方が変わるっていうのはあるなと思います。
Q)もうなかなか、終わらない文学談義になってきました(笑)。作品やキャラクターについて話していると、いつの間にか向きあったひととひととの話になっている。文学談義を通じて、相手が何を考えているのか、だんだん分かってくる。
A)いま、理系・実学ばかりがもてはやされていて、大学院で文学なんか研究して何の役に立つのっていわれますが、理系のひとも文系のひとも、人間であることには変わりないじゃないですか。その人間がいかに複雑に、さまざまな要素が絡んだ存在なのか、その要素のオリジンがどこにあるのかとか、そうした個人の問題が、いかに社会に反映されていくかとか、人間について学ぶことは誰にとっても大切で、面白いことだと思うんですよね。
Q)それをこそ、今後杉田さんが、英米文学の研究を通して、一般社会に発信してゆくところなんでしょうね。
A)そうですね、そうかもしれない! わたしがいいたいのは、文学はいかにひとの役に立つかということなんです。他の意見を受け入れようとする心持とか、自分のなかの混沌を整理するための実践的な方法とか、自分の考えをわかりやすく、説得的に相手に伝えるための、言葉の操り方だとか。自分自身や、他者、社会との間の軋轢を和らげる方法を教えてくれると思います。
Q)頼もしいですね! われわれより上の世代の人文学者だと、「役に立たないところが素晴らしいんだ」と逃げちゃうところなんですが、杉田さんの世代の研究者が、胸を張って「役に立つ」といってくれると、ぼくらも頑張らなきゃなと思います。最後に、何か話し足りなかったことなどはありますか? とくに、これから大学や大学院に進学するひとたちに。
A)そうですね…。先ほどもお話ししたとおり、わたし自身そうだったのですが、中学や高校での勉強が肌に合わなくても、大学で勉強の面白さに気づくこともあるので大丈夫ですよ、とはお話ししておきたいですね。
Q)中学や高校で辛くても、大学まで来れば本当にやりたいことが見えてくる、世界が開けてくることもありますよ、と。それは実体験ですもんね。
A)中学や高校の先生にも、本当に感謝はしているんですけれども! カリキュラムや制度の問題ですね。逆に、高校で成績がよかった友人たちのなかで、本当の目標を見つけられないでいる子もときどきみかけるので。だから、そんなにテストの点数ばかり気にするなよって。
Q)教員も、テストの点数ばかりみずに、生徒さんの人間をきちんとみてくれよってことですかね(笑)。今日は本当にありがとうございました!
A)ありがとうございました!